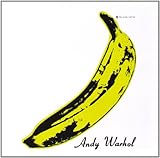「The Velvet Underground 」The Velvet Underground & Nico
早起きした日曜の朝は、このアルバムを聴きたくなる。
私がいちばん繰り替えし聴いたアルバムは、コレだと思う。
はじめてこのアルバムを聴いてから、十年の月日が優に過ぎているけど。今でもヒトリの夜に、早く起きすぎてしまった手持ちぶさたの「SUNDAY MORNING」に、このアルバムをよく掛ける。よくよく掛ける。私がこのアルバムを忘れてしまうことなど、あり得るわけがないのだから。その度に、と、思い返してみるのだけれど、私のカラダは、ノーミソは、おんなじように変わっていくみたい。そんなことに今日、気がついた。
このアルバムは、私のカラダを変えてくれる(もしくは戻してくれる)。私のノーミソを変えてくれる(同上)。それは十年だった今でも変わることがない。
近頃、インテリア雑誌なんかを眺めていると、このアルバムのジャケットーあの有名なウォーホルのバナナーがCDラックにオシャレ然として飾れている場面に、出くわすことがよくある。
それを見かける私は、いつだってちょっと笑いたくなる。その部屋が、何だかひどく俗っぽくって薄っぺらくって格好悪く見えてしまうから。
そうなんだ。このアルバムを取り巻く雰囲気は、いつだって雑多で薄っぺらいのだ。それはこの一枚のアルバムに限ることはなく、いろんなことで言えると思う。この世にもう、特別なものなんか残されてないのに。まだ私たちは目をぎらぎらさせて探し回っている。その浅ましさと薄っぺらさ。ヘンリー・ダーガー然り、鈴木いづみ然り(もっともっとあるのだけれど)。
そしてまた気がつくのだ。
俗っぽく薄っぺらで格好悪いのは、その物ではないということに。それらを見つけ出し、群がり珍しがって踏み荒らしていく私たちなのだと。そこに「物語」を見つけては、ありがたがる私たちなのだと。だから、見誤ってはいけないのだ。それらの底のところを。そのモノたちは、まるで台風の目のように静謐で、澄んでいるということを。黙って「作品」としてそこに「ある」ということに。
私が十年と少し前、このアルバムを手に取るきっかけになったいきさつは、今でもしっかりと覚えてるけれど。それをここで書くことは、今はしたくない。それは私の「物語」を語ることになってしまうから。
それでも。私の耳元で「VENUS IN FURS」のルーリードの真似をして歌ってくれた彼の声や。あの日見た空の色や。カーテンの揺れる様や。交わしたキスや。そんなことをフラッシュバックのように思い出したりもする。
そしてその思い出もみんな、このアルバムに溢れる音が流し去ってくれるのだ。
カリカリカリカリとコトコトコトコトと高まりながら、「ALL TOMORROW PARTY」「HEROIN」と、私をクライマックスに導いてくれる時、私の手足はだんだんにチカラを失ってく。入れ替わりに高鳴っていく心臓と、冴えていく意識だけを私は感じる。
「THERE SHE GOES AGAIN」「I'LL BE YOUR MIRROR」でヒトツ息を吐き、少しだけ私を開放してくれるけれど。そんな自由も束の間で。
「THE BLACK ANGEL'S DEATE SONG」で音はまた私のノーミソを引っ掻きだす。キュリキュリキュリ。そして「EUROPEAN SON」へと。キュリキュリキュリ。私の心臓はスピードは増し、息が上がって、擦られ続けたカラダはクタクタになる。終いには私は心底疲れ果てて、この音が止んで欲しいのか続いて欲しいのか、分からなくなる。この音が気持ち良いのか、苦痛なのかも、分からなくなる。
そして音が止む。
私はそこに放り出されて、トクトクトクと鳴っているのが、自分の心臓だと気がつくのだ。その音に包まれながら、私の頬は上気して、呆けたような顔をしているんじゃないかと思う。
2003-02-23/巻き助